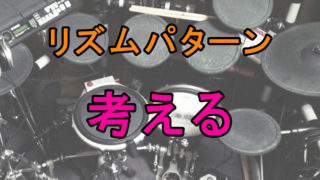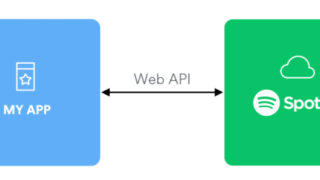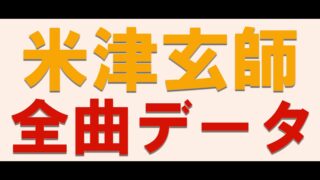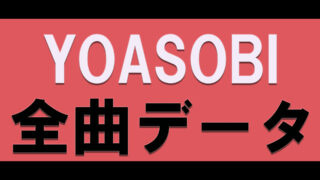今回のテーマは、「自分は、”自分の意思”通りに行動してくれない。」です。
“自分の意思“の過大評価をやめる

多くの人は、わりと“自分の意思“みたいなものを過大評価していると思います。
実際の人間の行動は「習慣」、「環境」や、「本能」みたいな「”自分の意思”とは違うもの」にかなり左右されるようです。
したがって、「きっと1日の間、“自分が自分でいられる時間”(=自分が”自分の意思”の支配下にある時間)は、そんなに長くない。」と僕は捉えています。
たとえば
- 「ダイエット中に余計なものを食べちゃった」
- 「遊んじゃって勉強が捗らない」
みたいな話はよくありますよね。
「自分が”自分の意思”の通りに動いてない」好例だと思います。
“自分の意思”は2,3割?

普段の行動の約45%が習慣によるもの、約30%は睡眠らしいです。
こういうデータからも、「”自分の意思”とはちょっと違うもの」で自分が動いていると伺えます。
脳科学的にも、習慣は「大脳基底核」、理性は「前頭葉」が関係しているらしく、司っている部分が違うようです。
そして、疲れてくると理性を司る「前頭葉」の動きが鈍くなり…行動が習慣に紐づいたものに切り替わっていく… と。
つまり、「自分という乗り物」の操縦者が”自分の意思”ではなく”習慣”というオートパイロットに切り替わる感じらしいです。
対策方法は?
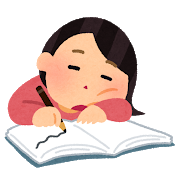
じゃあ、どうすればいいのか。
”自分が自分でいられる時間”の内に、「そうじゃない時の自分」が概ね”自分の意思”の望むように動いてくれる仕組みを考えて実行しておくのが有効だと思います。
つまり、“自分の操縦桿”を自分が握っていられる時間のうちに、自分のオートパイロット(習慣)のプログラムを作るっていう発想です。
たとえば、「南側に崖がある場所の近くに自分が居て、そのうち意識を失ってランダムな方角に走り出す」状況が前もって分かっていたとします。
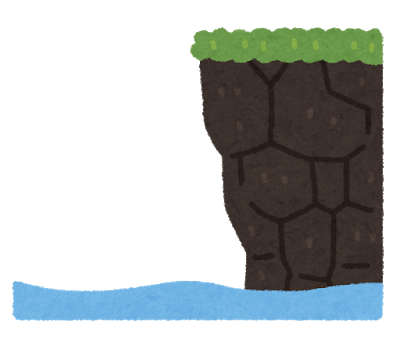
この状況下で確実に崖に落ちないためには、崖がない方角に走る確率に賭けたり、気合いで意識を保とうとするよりも…
「自分が”自分の意思”を保ってるうちに、谷ある南の方角に自分が越えられない”壁”を作るなどの対策する方が確実に落下を防げるよね」っていう発想です。
そして、日常生活で壁“の役割を果たすのは”習慣“になります。
つまり、“悪い習慣”を“良い習慣”に修正していけばいいのです。
じゃあ、どうやって”良い習慣“を自分にプログラムすればいいのか……
“習慣”をプログラムするには
ノルマを小さく設定する
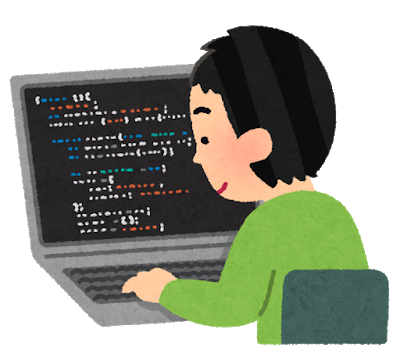
脳は大きな変化が苦手らしいく「最初はノルマをものすごく小さく設定する」のが有効らしいです。
たとえば、ダイエットなら…
いきなり食事制限や高負荷の運動をするのではなく、「いつも食べている量からちょっとだけ減らす」とか、スクワットを絶対1回やる とか。
楽器の練習なら…
「いきなり 数時間やる!」みたいなやり方じゃなく、「毎日 数分楽器を持つ」だけから始める とか。
小さい目標を設定して、徐々に時間を増やしていく方が結果的に挫折し辛く、習慣化しやすいです。
(そして、大体2か月くらい継続すると習慣になるのが通説っぽいです。)
また、もし守れない時があった場合は「自分を責めずにさらに目標や環境を整備する」のが大切です。
悪い習慣も同じメカニズムで形成される

つまり…習慣が形成されるメカニズムを考えると…
お酒やタバコやギャンブルなど悪い習慣の鉄板誘い文句である「1回試しにやってみな」とか「ちょっとだけ付き合えよ」は想像以上にヤバいと言えそうです。
もちろん、「たくさんやってみな」も普通にヤバいので「私は一切やらない」だけが正解です。
実際の体験例
僕は、10年以上基本的に毎日ランニングしています。
しかし、これは別に意志の力ではなく、習慣の力だと思います。
実際、走り始めてから帰って来るまで半分自分が自動で動いてるような感じもします。
思い返してみるとランニングを始めた最初のころは5分も走れませんでした。
しかし、今は毎日5㎞をキロ5:30~6:00ペースで走っています。
始めた当時は「こうやって続ければ習慣化してうまくいく」などは思っていませんでした。
しかし、「毎日ちょっとずつでもやろう」と思って始めたので、知らないうちに習慣化するためのプロセスを踏んでいたのかなと思います。
その他 補足
あと、環境の話をすると人間はやろうと思ってから5秒以内に実行に移さないと実行するハードルがとても上がるらしいです。
したがって、実行のハードルになりそうな環境を整えておくのも大切だと思います。
たとえば、楽器が上手になりたい時は、自分の手の届く範囲に楽器を弾ける状態で置いておくのはわりと有効な方法かなと思います。
(だから、僕は大体「楽器がどうすれば上達するか?」に対しては、「近くにすぐ弾ける状態の楽器を置くと良いと思う」と答えます。)
さいごに
というわけで…
「自分はあんまり”自分の意思”で動いてないから、それを踏まえた上で自分が”自分の意思”が望むように動いてくれるにはこんな感じで工夫すればいいんじゃないか」
という話でした。
僕も僕を僕が望むように動いてくれるために、これからも工夫を重ねたいと思います。笑