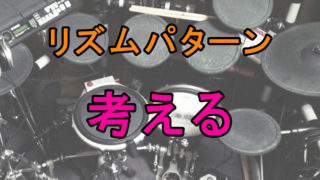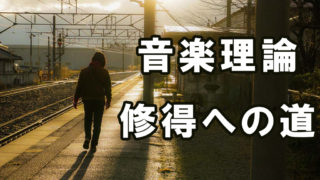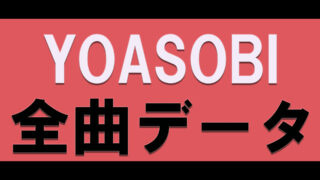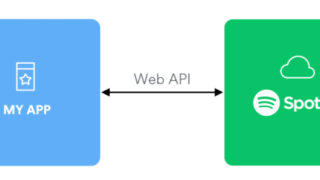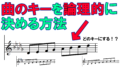この記事は、僕が音楽についてふと考えたことを書いた内容です。
かなり思考が散らかっている自分用のメモで、学術的に正しいかどうかは分かりません。
西洋音楽では、音楽の三要素は「リズム・メロディー・ハーモニー」と言われていて
・歌や主旋律を指して「メロディー」
・伴奏やハモリによって生まれる音の重なりを「ハーモニー」
・主にパーカッションやドラムの音のリズムパターンを指して「リズム」
みたいな感じ。
つまり、それぞれが音楽に対する抽象になっている。
しかし、当然この三つの要素は完全にに分離したものじゃない。
リズム・メロディー・ハーモニーは「音楽を捉えるための三視点」であると考えるとある意味スッキリする気がする。
メロディー
理論上の”正弦波“でなければ、全ての音には「倍音」が存在している。
つまり、「メロディー」は「ハーモニー」を内包していると言える。
また、「メロディー」は「リズム」と「音高」が合わさったもの。
だから、「リズム」も「メロディー」に内包されていると言える。
捉え方次第では音楽は、「メロディだと思われている音」と言えそう。
ハーモニー
音楽は時間芸術。
スペクトラムアナライザーで瞬間を切り取られた音楽は
・「メロディー」として鳴る音と「倍音」
・「メロディー」の「倍音」の装飾である「ハーモニー」
・「メロディー」にエネルギーを付加する「非整数次倍音(リズムに多く含まれる)」
に見える。
ある意味、瞬間的に切り取られた音楽は全て「ハーモニー」と言えそう。
リズム
逆に、瞬間的な「ハーモニー」を時間的に連結したものを「リズム」と考えられそう。
時間の流れが無ければ「リズム」は分からない。
反対に時間の流れで、音楽を見ると「リズム」の存在感が大きくなる。
人間の分解能で捉えられるリズムを「リズム」、
人間の分解能で捉えられない高速のリズムを「音高」として捉えているのだろうか?
「コード」や「音高」も、とても短いオーダーで考えると「リズム」とも言えそう。
「音」は媒質が振動する「リズム」のレイヤーなのだろうか?
ただ、時間を意識した時点で、そこに「リズム」はある
あとは「時間」という「リズム」の原石の中から、どのような情報を切り出すか。
みたいな感じかもしれない。
音楽は人間のもの
音楽には「数学や物理で捉えた場合は同じものだけど、人間のスペックや分解能に合わせるために別の概念や表現になっているもの」が結構ある。
そして、それが音楽の定義を曖昧にしているような気がしたりしなかったり。
何か音を意識した時点でそこに「音楽」はある。
あとは「音」という音楽の棚からどういう音を選択して組み合わせるか。
そんなイメージ。
【追記】
…みたいなことを考えた延長線上で、こういうアイディアを思いつきました。笑