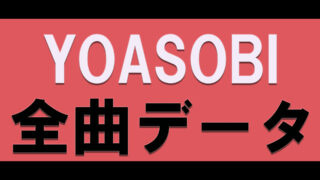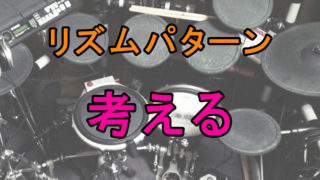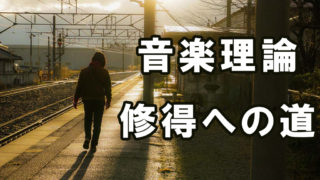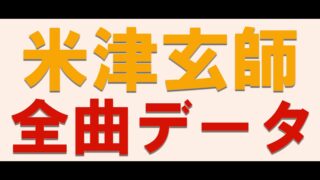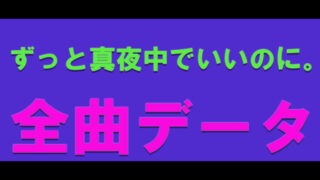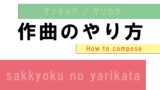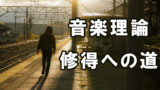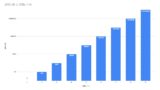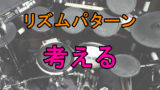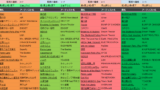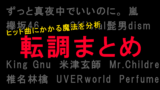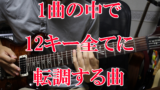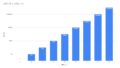10年以上曲を作ってきて思う”作曲のコツ“についてまとめました。
手の内を晒しまくっています。
しかし、それは同時に個人の偏見に塗れているわけなので その点はご了承ください。笑
↓ちなみに作曲初心者の方は、まずこちらの記事に目を通していただいた方が良いかもしれません。
では、いってみよう!(๑˃̵ᴗ˂̵)و
メンタル面
「…あれ?作曲のコツじゃないの?」と思うかもしれません。
ただ、曲を作る・作らない以前に創作活動は自分との戦いです。
たしかに、瞬間的な熱意も大事です。
しかし、まずは粘り強く作り続けるための精神と環境(習慣)づくりが大切だと思います。
というわけで、最初はメンタル面について書いていきます。
「良い曲を作ろう」と意気込み過ぎない 。
昔、「良い曲を作ろう」と意気込んで全然曲を作れない時期がありました。
でも、「別に完璧なものを作らなくてもいいか」と思い始めてから、比較的早く曲を作れるようになりました。
したがって、手を抜くのではなく“肩の力を抜こうとする気持ち”は大切だと思います。
もちろん、冷静に振り返ると 技術の向上などその他の要因もあったと思います。
結果的に作品を完成させると経験値も溜まりやすくなります。
「曲の完成度」よりも「曲の完成」が重要
とりあえず、「良い曲を作る」よりも「曲を完成させる」方が大切だと考えましょう。
僕の体感としては、創作活動を始めたものの作品を完成・公開まで到達できる人はわずかだと思います。
“作品を完成させて公開するまで辿り着く“自体が、かなり大きなハードルであり特別だと意識しましょう。
100曲くらい完成させれば、その頃には完成度も自ずと上がっているはずです。
自分の中で「自分の曲の価値」を上げすぎない
人間には「イケア効果」という認知バイアスがあります。
イケア効果(IKEA effect)とは、自分が作ったものや関与したプロジェクトに対して、その価値を過大評価する心理効果のこと。
シマウマ用語集
人は手間をかけることで思いや愛着が強まり、自分のみならず他人にとっても高い価値を持つものと錯覚する効果がある。
自分が一生懸命作った作品はどんなに拙くても、大切で良い作品に思えます。
しかし、他人はそんな作品に対して酷評したり、無関心だったりする場合がほとんどです。
「イケア効果」を自覚すると、多少なりともその心理的ダメージを軽減できます。
…まぁ、悲しいものは悲しいですけど。笑
「曲を作る練習や勉強をする」という発想をする。
たとえば、楽器を弾くには練習や勉強が必要ですよね。
楽器を始めた日に いきなり 「プロ並みに楽器が弾けるかも!」と思う人はいないと思います。
一方、作曲は「最初からそこそこ良い曲が作れるんじゃないか?」と思ってしまいがちます。
しかし、少なくとも僕は
楽器と同じで作曲にも練習や勉強が必要だと考えます。
たしかに、”曲の良し悪し“は、”楽器演奏の上手さ“よりもさらに“良し悪しを測るモノサシ”が曖昧です。
だから、
- 「音楽理論が分からなくても、感性で良い曲を作った人もいる!」
- 「楽器が全く弾けなくても、良い曲を作れる才能がある人もいる!」
みたいな意見が出てくるのは理解できますし、この意見を完全には否定できません。
僕自身も“メロディを作る”=”作曲”とするのなら「あり得るのかもしれない…」とは思います。
しかし、「編曲やミックスまで含めた音源の完成」=「作曲」とする場合やはり信じがたい話です。
それに、最初から優れた能力を持った人でも練習や勉強で能力を伸ばせる余地はあるはずです。
ちなみに、「勉強すると、オリジナリティを無くす」という考え方もあるようです。
しかし、「勉強して無くなるオリジナリティ」など、所詮はその程度のものです。
気にせずに勉強しましょう。
「才能」や「感性」の話
音楽をする上で、「才能」や「感性」に関わる話はよく話題に上ります。
色々な考え方を知るのは面白いですし、ためになる部分も無いとは言えません。
しかし、これらは定量的に考えるのがとても難しい要素です。
音楽をやる時に、あまり真に受けすぎない方が良いと思います。
たとえば、僕は小さい頃『全く音楽の「才能」が無い」』と言われましたし、音楽に対する「感性」も未だによく分かりません。
でも、今はこんな感じ↓で楽器を弾いたり曲を作ったり、音楽をそれなりにはできています。
「才能」や「感性」 の話も良いですが、地道に勉強や練習を重ねて出来る要素も多いかと思います。
↑…この僕の意見も含めて参考程度にとどめて、どれも真に受けすぎないくらいがちょうど良いのでは? と思います。
巨人の肩に乗っていることを自覚する
Googleの論文検索サービス、「グーグルスカラー」のスローガンにも使われる「巨人の肩に乗る矮人」という言葉があります。
これは、「先人の積み重ねた発見に基づいて何かを発見すること」を指します。
音楽も同様に、先人の実践の積み重ねの上に成り立っていると思います。
したがって、色々なものからインプットしようとする姿勢が大切ではないかと考えます。
また、インプットを通して「自分のオリジナリティは、過去の膨大な歴史の上澄みにすぎない」と実感すると、謙虚でいられる気がします。
病まないため・長く続けるためにも外部からインプットする
そもそも、外部からのインプットに頼らず、自分の内面から湧き出るものだけで作品を作ろうとするのは危険だと考えます。
自分を材料に作品を作るのは、いわば補給を絶たれたアンパンマンみたいな状態です。 笑
歴史上の芸術家の人生を見ると分かりますが、芸術家は病みがちです。
そういう危険を回避するためにも、この考え方は必要だと思います。
健康になろうとする
ミュージシャンと言えば、お酒やタバコをやっているイメージがあるかもしれません。
しかし、主なデメリットを挙げるだけでも
- お金がかかる
- 時間を浪費する原因になる
- 健康に悪影響がある
- 思考力を奪われる
- 依存性がある(やめたくなっても簡単にはやめられない)
合理的に判断すれば、飲酒や喫煙をやるべきではないのは明らかです。
少なくとも僕はどちらも一切やりません。
代わりに、できるだけ心身を良い状態に保つため、十分な睡眠・バランスのとれた食事・適度な運動を心がけています。
ある意味、一番の作曲のコツは「心身ともに健康で長く続ける」だと思います。
具体的に僕が実践している主な内容としては
- 睡眠時間は7~8時間以上を確保する。
- 間食やお菓子類は食べずに腹8分目に抑える。
- 毎日5kmのランニングと軽い筋トレ、ストレッチをする。
です。
※運動に関しては、最初から高い負荷をかけ過ぎると長続きしないと思います。徐々に慣らしていって習慣になれば無理なくできるようになるはずです。
(毎日ランニングは15年以上続けていますが、最初は1kmでもまともに走れませんでした。)
あとは、「体調が悪い・体が痛い」場合は潔く休むのも大切です。
ときに、生死をさまようギリギリの状態から生まれた作品がもてはやされる場合もあります。
しかし、あなたが既にそういった状態でないのなら、わざわざ自分からそんな芸風に突き進む必要は無いと思います。
環境面
人間は怠惰です。
楽なものに流されまくります。
いわば「理想」という名の水源から、下流はおろか海まで流される勢いで怠惰です。笑
では、どう対策すればいいのか。
ひとつの答えは「環境を整える」だと思います。
5秒以内に作曲が始められる環境を整える
人間はやろうと思ってから5秒以内に実行に移さないと、実行するハードルがとても上がるらしいです。
(参考:自分をだますのを止める方法 | メル・ロビンス | )
したがって、「作曲をしよう!」と思っても、5秒以内に行動を始められなければ「やっぱ今日はやめとこ」となる可能性が高くなるわけです。
僕は、作業部屋の椅子からほぼ動かずに楽器を弾く、資料を読むなど作曲を含むほぼ全ての作業を実行できる環境にしました。
怠けを”ゼロ”にできたわけではないと思いますが、効果はあったと思います。
if-then プランニング
if-then プランニングは、「(if)Xしたら(then)Yする」という形で具体的に自分がやる事柄を予めメモとして書き出しておく手法です。
if-then プランは、目標達成の障害物への具体的な対策を含んだ内容にするのがポイントです。
【例】
- △曜日の××時になったら、2時間タイマーをセットする。
- DAWを起動して2時間作曲をする時間をとる。
- スマホは手の届かないところに置く。
- コード進行のアイディアが煮詰まったら、○○を読む。
- メロディのアイディアが浮かばないときは、○○する。
- 2時間経ったら、どんなに途中でも強制的に保存して終了する。
- ……
脳が状況判断に余計なリソースを使う必要が無くなり、目標の達成率と集中力が上がります。
食事や家事など既に自分が習慣的に行っている行動の後に繋げて、if-then プランを組み込むのもオススメです。
繰り返す中で自分に合うようにさらに改良を加えて、できるだけ作業の実行ハードルを下げていきましょう!
テンプレートやショートカットを使う

現在の作曲作業の大半は、コンピューターや機材の操作です。
では、そのコンピューターや機材の操作は「クリエイティブな行為」でしょうか。
ほぼ違うはずです。
今、自分がやっている作業の中で、簡略化・システム化できるところは徹底的にやりましょう。
少なくとも、テンプレート機能やショートカットは必ず使いましょう。
僕はDAW(作曲ソフト)に限らず、ソフトの使い方を勉強するときは、本気でショートカットキーを覚えるのが大切だと考えています。
たとえ、ほんの5~6秒の短縮でも1万回やれば1時間の差があります。
そして、余分な細かい動作の積み重ねはクリエイティブな体力・集中力を奪います。
僕のDAWテンプレートは
- 空間系のプラグインのルーティング
- FXチャンネルの設定
- ソフトシンセのパラアウトの設定
- よく使用しそうなトラックのセットアップ
など普通にやると30時間分くらいかかるエンジニア的作業を既にやった状態にしてあります。
つまり、最初から 約30時間分の作業・処理が終わった段階でDAWが立ち上がります。
もちろん、そのテンプレートの内容を毎回全て使うわけではありません。
しかし、ゼロからDAWを起動するのに比べて、少なくとも数時間分の作業時間短縮につながっていると感じます。
作曲面

ここからいよいよ作曲自体の内容に入っていきます!
バランスを意識する。
作曲は、「単純と複雑」のバランス感覚が重要だと思います。
たとえば
- 「メロディを複雑にした場合は、伴奏をシンプルにする」
- 「伴奏が複雑な場合は、リズムはシンプルにする」
みたいに、どこかを複雑にした場合は他のどこかは複雑にしない方が “キャッチー” になりやすいです。
もちろん、”キャッチー“が必ずしも良いわけではありません。
このような観点を持つのが大切ではないか という意味です。
BPM(テンポ)
自分の中で、BPMの違いによって生まれる音楽的な効果を意識しておくと迷いにくいです。
僕の場合はこんな感じで、おおまかに20刻みでイメージをもっています。↓
- ~110:全音符から32分音符まで使える。
- 130前後:16ビートでノリノリ。踊れる曲に使う。
- 150前後:テクいことをしやすい。倍テンでアゲアゲ。ハーフタイムだとバラード。
- 170前後:シンコペーションで分かりやすいアップテンポ感を出せる。
- 190~:スクエアだと速過ぎて逆に遅い。シャッフル系で使うのがオススメ。
他には、「ダンスミュージックならこのくらいのテンポだな…」など、リファレンス(手本)となる曲のテンポ感を把握しておくと良いと思います。
キーの決め方
キーは
- ①曲に使用する楽器の特性
- ②ヴォーカル(またはメインメロディーを担当する楽器)の最高音をどう使うか
この2つのバランスを考えて決めます。
この記事↓に詳しくまとめました。
ジャンルを分ける要素を意識する
「ジャンルにとらわれない音楽をやっている」はよく聞く言葉です。
しかし、創作する立場ではそういうアーティストのセールストークに惑わされてはいけません。
「ジャンル」は、「メロディ」や「リズムパターン」や「コード進行」と同じく音楽を抽象化して眺める視点のひとつに過ぎません。

作曲する際には「音楽の要素」と「ジャンル分け」がどう結びついているか把握して、それを意図的にコントロールする必要があると思います。
たとえば…
- 歌詞
- メロディ
- リズム
- コード進行
- 音色やサウンド
- 楽器編成
- 歴史的な背景
など音楽に関わる要素が”どのようにジャンル感と結びついているか“を自分なりに考えて体系化すると、自分の意図する音楽表現がやり易くなると思います。

曲構成のバリエーションを考える
曲構成は、かなり大切なものです。
正直、僕が「作曲で一番悩む部分」はここです。
オーソドックスなものの一つとして
- イントロ
- Aメロ1-Bメロ1-1サビ1
- Aメロ2-Bメロ2-サビ2
- 間奏
- 落ちサビ-ラスサビ
- アウトロ
みたいな構成がよく挙げられます。
しかし、よく聴いてみるとこれにそのまま当てはまる曲はさほど多くなく、曲ごとに微妙に違っていたり、色々なパターンがあります。
たとえば…
UVERworld – ナノ・セカンド
この曲は普通に聴いていると、ただ勢いに任せたアツい曲にも聴こえます。
しかし、冷静に分析してみると、わずか5分弱に9個(!)の展開やモチーフを複雑に織り交ぜた緻密に計算された曲展開になっています。
以下、僕の解釈で書き出してみました。
| 展開数 | 展開 | リハーサルマーク |
| 1 | イントロ1(サックスソロ) | A1 |
| 2 | イントロ1-2(ワブルベース) | B1 |
| 3 | Cメロ(everything…) | C1 |
| 4 | サビ(それが幻想のままで…) | D1 |
| 5 | コール(just do it…) | E1 |
| 6 | イントロ2 | F1 |
| 7 | 大サビ(to be or not to be…) | G1 |
| 8 | Aメロ(千マイルの距離で…) | H1 |
| 9 | Bメロ(確かなことは…) | I1 |
| 10 | コール(just do it…) | E2 |
| 11 | サビ(その幻想のままで…) | D2 |
| 12 | Aメロ(一度も…) | H2 |
| 13 | Bメロ (もうここには…) | I2 |
| 14 | Bメロ (容易く叶う夢は…) | I3 |
| 15 | コール(just do it…) | E3 |
| 16 | サビ(なら幻のままで…) | D3 |
| 17 | 大サビ(to be or not to be…) | G2 |
| 18 | Cメロ(サックスソロ) | C2 |
| 19 | Cメロ(everything…) | C3 |
| 20 | Bメロ(考えてみろよ…) | I4 |
| 21 | Bメロ(人の数より少し…) | I5 |
| 22 | コール(just do it…) | E4 |
| 23 | サビ (その幻想のままで…) | D4 |
| 24 | サビ (なら幻のままで…) | D5 |
| 25 | 大サビ(to be or not to be…) | G3 |
| 26 | イントロ2 | F2 |
| 27 | イントロ1(サックスソロ) | A2 |
| 28 | イントロ1-2(ワブルベース) | B2 |
このように、どのセクションをどんな構成で連結していくか。
ある意味一番力量を試される部分かもしれません。
音楽はあらゆるレイヤーに「2の累乗数のまとまり」がある
僕は、音楽のセクションにはいくつかのレイヤーがあると考えています。
以下はそのレイヤーの種類と、基本的な尺をまとめたものです。
- 階層1.反復回数: 大楽節×2まわし
- 階層2.大楽節: 8小節(動機×4)
- 階層3.小楽節: 4小節(動機×2)
- 階層4.動機: 2小節(小動機×2)
- 階層5.小動機: 1小節 (≒拍子のまとまり): 4拍(≒4拍子)
- 階層6.1拍(≒4分音符): 16分音符 (1拍の4分割)
これを見ると、音楽はあらゆるレイヤーで2の累乗数※のまとまりが「基本」になっていると分かります。
※1,2,4,8,16,32…
作曲の際には、この「基本」踏まえながら必要に応じて変化を加えます。
「基本」を知る重要性
「基本」を知っていると、安定して作品を作れるだけでなくセオリーから外れた展開をする曲に気付けるようになります。
たとえば
THE BEATLES – Yesterday
この曲の冒頭のセクションは、「階層2.大楽節」が通常8小節のところ7小節しかありません。
このように「基本」との違いに注目しながら曲を聴くと、”ズラしている曲“に気付きやすくなり自分の引き出しも増えていくはずです。
モチーフを作るときに意識すること
メロディは、どんな種類の音楽にとってもとても重要な部分だよ、キャッチーなメロディが嫌いなやつなんているか?
Lee McKinney (BORN OF OSIRIS)
モチーフを作るときに、僕が意識していることを箇条書きにしてみました。
- 細かいモチーフをリフレインさせる。
- 歌メロの場合は音域を広げ過ぎない、狭い音域でも転調を使うなど対策法はある。
- ペンタトニックは王道
- ブルーノートは必殺技
- コードトーンに対してメロディがどの音程になっているか意識する。
- 同じ音を連続させる部分(同音連打)を恐れずに入れる。
- 盛り上げる前のタメを作る発想を持つ。
- 休符を入れる場所を考える。入れないと微妙になる場合が多いし、息継ぎしにくい。
- モードや対位法的なアプローチも試してみる。
参考:美しい音楽は、メロディの反復と旋律のパターンから。
・非和声音や装飾音(オーナメント)を意識する
- 刺繍音:同じ音の連続の間に2度の音を挟む。
- 倚音:コードトーンへ行く前に置くノンコードトーン。
- 経過音:2音間を繋ぐ音。半音でつないだり、ポルタメントしたり。
- 先取音:和音の変わる直前に、次の和音の構成音から先取りして鳴る音。
- 逸音:順次進行の間に置く、逆に順次進行する音。(例:レ→「ド」→ミ)
- 掛留音:コードが変わっても持続的に鳴っている音。
メロディをピッチクラスの変化で捉える
別記事で、違う視点からメロディを分析したものがあります。
リズムの作り方
「曲に対して意図した効果を付加できるリズムを、選んで組み合わせる」 ことを考えます。
詳しくはこちらの記事↓に書きました。
モチーフ展開のアイデア
作ったモチーフを、曲中で一部変化させて繰り返し使うのも有効な手段です。
そのアイデアとしては…
・ “リズム“か”音の並び“のどちらかを変える。
- “リズム“を一部変える場合は、シンコペーションや音価を変えるのが手軽。
- “音の並び“を一部変える場合は、メロディの最後などは変えやすい。
・後ろで鳴っているコードを変える。
KHUFRUDAMO NOTES – Aerial Warfare
拙作。0:29あたりからのモチーフと、3:18あたりからのモチーフは
メロディーが同じですが、コードは違います。
・メロディを反復する際に、一回し目の最後をニ回し目のアタマまで拡張し途中から2回し目のメロディに入る。
モダンメタルでよく使われる手法です。
シンコペーションの逆みたいな発想です。
Polyphia – O.D.
この曲の最初モチーフは、0:14あたりでニ回し目に入ります。
ただ、一回し目にはあったモチーフのアタマ部分が2拍ほど削られています。
ハモリの考え方
基本的にコードの構成音と度数のイメージから考えます。
- 3度・6度ハモリ … 一番王道で、ポップスではまず試してみる。
- 4度・5度ハモリ … 無機質な感じや、エスニックな感じになる。調性感が薄れる。
- 2度・7度ハモリ … 音がぶつかっている感じ。攻撃力や緊張感が高い。
大まかにこんな感じのイメージです。
個人的にはワンフレーズをメロディに対して同じ度数のハモリで押し切るより
コードトーンとの整合性を考えて柔軟にハモリを付けた方が良い結果になる気がします。
バッキングのアイデア・コードの切り替わりのタイミング
コードの切り替えタイミングだけでも、さまざまなアイデアが考えられます。
むしろ、それによって大きく曲の雰囲気は変わってきます。
- 小節ごとに変える。
- 小節の半分のところで変えていく。
- 1拍ごとに変えていく。
- 4小節目だけ小節の半分のところで変える。
- 2,4小節目だけ小節の半分のところで変える。
- 1,3小節目だけ小節の半分のところで変える。
↑これらのタイミングにシンコペーションなど絡める
- 4小節目だけメロディや対旋律っぽくする。
- ペダルポイントを使う。
- リフを弾く(コード進行ではなくリフだと解釈する。)
- 対位法的に考える。
- 「そもそも、コード進行など幻想であり存在しない」と考える。笑
転調
曲の途中でキーを変えることを転調と言います。
転調を使うと曲の雰囲気を大きく変えたり、狭い音域でもさまざまなメロディーを展開できたりします。

具体的な作曲解説
KHUFRUDAMO NOTESの『KEGON』を実際に話しながら動画で解説しました。
結構ガッツリ説明しているので長いです。
参考にできそうなところは参考にしてみてください。
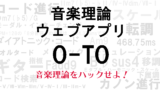
和風な曲が作りたい方は、こちらの記事↓も参考にしてみてください。